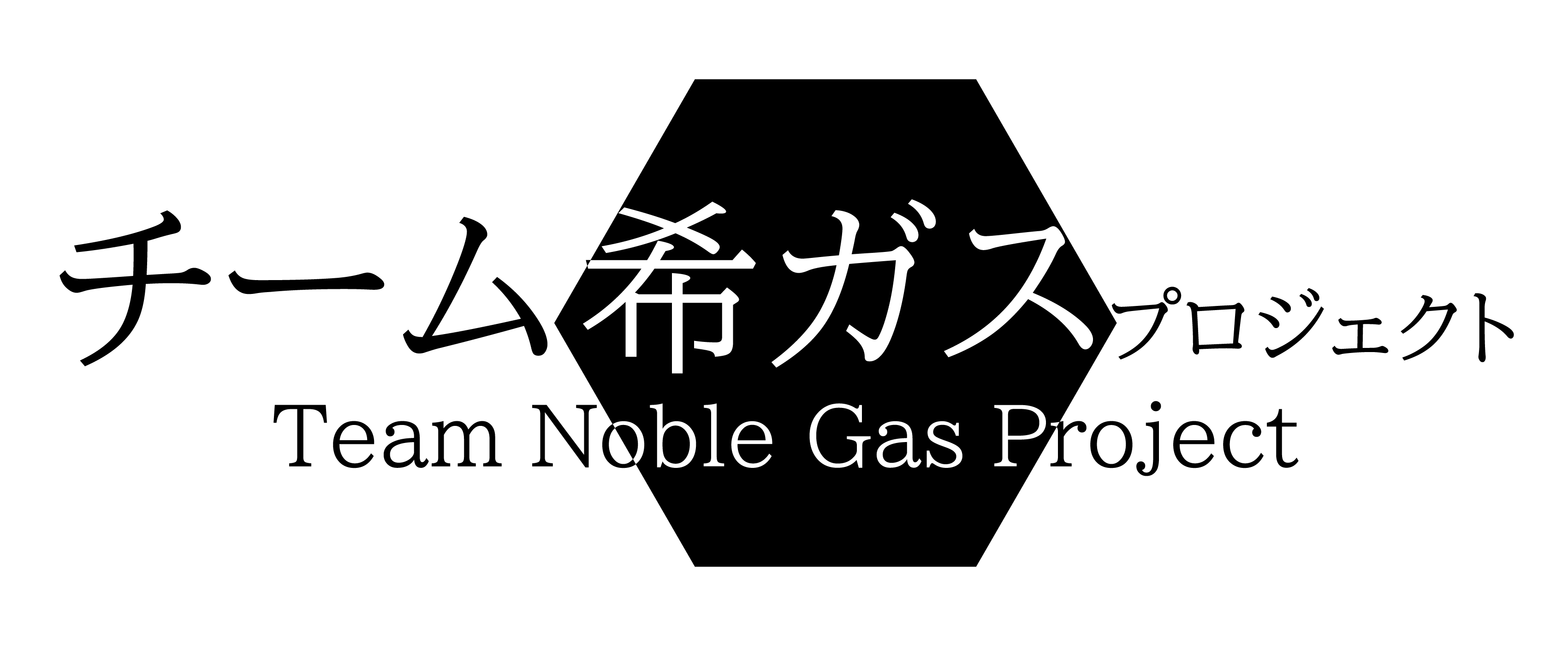共に歩む者たちへ
こんなつもりじゃなかった! キセノンの青色の光の中で、僕は叫ぶ。 彼には幸せになって欲しかったのに! 僕は右手を見る。繋いでいたはずの手はもちろんない。 僕の寂しさで誰かを殺してしまうなんて、僕は本当に最低だ! 体がもう一度世界に還るために準備を始めた。 もうあの街には戻りたくない。 青色の光が僕を導いていく。 せめて生まれ変わるなら、彼と心中したあの街より、できるだけ遠くに行けますように。 僕はそう思い、目の前に浮かぶ五十四番のゲートを通った。 気がつくと、そこは腐ったい草の匂いが充満する小さな古民家の畳の上だった。 僕……キセノンは、ごく僅かだが大気中にも存在するため、どこで生まれ変わるかは正直運だ。 まだ生まれ変わったばかりの小さな体だと散策も不便だが、一ヶ月ほどで僕らは少年くらいの大きさには成長する。 服を探さなければ。そう思って、ウロウロと歩いてみる。 幸いにもここは、誰も住んでいない空き家のようだった。 ……夏の風が隙間から入ってくる。 少し湿っぽい潮風の香り。 ヒビがたくさん入り、ところどころ割れた窓ガラスの方を見ると、真っ青な海が見えた。 「海辺の町なのかな……」 僕はとりあえず服や布切れなどを探した。 小さな一枚布を体に巻いて、とりあえず全裸は回避する。 「……ネオンの彼は」 前の世代で一緒に死んだ……心中してしまった彼の顔を思い浮かべる。 どうしても、悲しそうな、でも頑張って笑顔を作る少し幼なげさを残した彼の姿が、目に残って離れない。口の中に注がれた、彼の血の味を今でも思い出せる。 「いや、思い出すだけ辛いだけだ」 潮風に微かに雨の匂いが混じる。少しずつ暗くなっていく空を見て夕立でも降るのだろうと思う。 「そういや生まれ変わったら、名前を考えなきゃいけないんだよね……」 どんなに自分の名前を考えようとしても、ネオンの彼の名前が浮かぶ。 「キセノンだし、喜瀬でいいかな……下の名前は後で考えよう」 強い雨が、屋根を叩く音がする。 どうしても。こんな湿っぽくよどんだ空気の中では、僕の心も晴れない。何より、心を埋め尽くす寂しさに襲われる。 いやだな。 もう、自分の寂しさのせいで、誰かが死ぬのは嫌だ。 幸いにも世界は広い。こんな中で、たった百人やそこらのうちの誰かが、僕を見つけるなんて不可能だ。 ただ、それでももし僕を見つけてくれる人がいたら…… 「その人は、きっと僕の運命だ」 落ちていたボロボロのクッションに体を預け、激しく降る夕立の雨音を聞きながら僕は深い眠りに落ちていった。 ……僕が生まれ変わってから、数年が経っていた。 どうやら、僕の生まれ変わった島は、人口三百人にも満たない島らしい。 自転車で一周できるほどの大きさの島で、僕はのんびり暮らしていた。 朝は釣り竿を持って海岸に行き一日分の魚を獲る。 時には庭のバナナを取って食べたり、魚が大量のときはご近所に配って調味料やお米を分けてもらう。 不便なところももちろんあるが、のんびりと暮らすにはいい島だ。 コンコンと音がする。 「喜瀬さんや」 もう割れてない窓ガラスを縁側から叩いてくるおじいちゃん。 「あ、高橋さん。こんにちは!」 畳で横になってた僕は、読んでいた本を横に置き、縁側の窓を開ける。 「ちょうど今雨乞いの祭りをしておっての、お餅のお裾分けじゃよ」 そういって、タッパーの中を見せてくれると、あんこやきなこをまぶしたお餅が入っていた。 「わぁ!ありがとうございます!お餅大好きです!……そういえば、本当に今年は雨が降りませんね」 こんなダムを作ることもできない小さな島では、水不足は死活問題だ。 「今までそんなこともなかったがの、あれかね、地球温暖化とかいうやつかね」 高橋さんは縁側に腰掛けながら言う。空はよく晴れて、強い日差しが降り注ぐ。日差しを避けるように、高橋さんは日陰を探していた。 僕は、台所から麦茶の入ったグラスを二個持ってきて隣に座った。 「最近は夕立も降らなくなりましたし」 空を見上げると、入道雲の一つもない青すぎる空だった。 「まあワシらに任せとけって、ワシらの雨乞いは世界一じゃでの」 「……そうですね」 僕はきなこ餅を一つ摘むと口の中に入れる。 パサパサと乾いた口当たりが、どうにも最近のこの島の状況に似ていると連想してしまう。 「まぁ、困ってる時はお互い助け合いが必要じゃけ、喜瀬さんも困ったことがあったら頼るがいいね」 そう言って、高橋さんは立ち上がり去っていった。他にもお餅を配る先があるらしい。 困った時は助け合いが必要。 どうして、今になってあの顔が浮かぶんだ。 僕は、頭を抑えながら、しっとりとしたあんこ餅を口に運ぶのであった。 雨乞いの儀式は大成功だった。 ……いや、成功しすぎたと言っても間違いないだろう。 あまりの降水量で、島が沈没しそうな勢いの雨が地面を叩く。 すでに住民の大半は島から本州への避難船に乗り込んでいた。 僕は、ためらっていた。 ここから脱出して、もし他の元素に会ってしまったら? そう思うと、なかなか船に乗る度胸が湧かない。 しかし、家もすでに浸水してしまった。船着場にいる高橋さんが、僕を呼ぶ。 「おい、喜瀬さんや、もうこれが最終便での、乗りなさい」 そう促され、僕は渋々船に乗る。 どうせ、この雨がやめば帰ってこれる。すぐに戻ればいいんだ。 家のことはどうにでもなる。そう覚悟を決めて、僕は船に乗り込んだ。 だんだん、島が遠くなる。 激しい雨で、島はすぐに雨のかすみの中に消えていった。 船は揺れる。波がひどく高い。僕は船酔いはしないが、流石に船が心配になる。 見渡してみても三百六十度視界が悪い。 嫌な予感がする。 僕はそう思い、船の向かう先を見る。 なんとか、朧げながら陸地の影が見えた。だんだん濃くなっていくその影に、僕は安堵のため息をつく。 思い過ごしだったかな。安心して柱にもたれて右を見ると、そこには。 巨大な波が、船に魔物のように襲いかかってくるところだった。 ……どれくらい気を失っていたのだろう。 船を飲みこむほどの大きな波により揺れた船から投げ出された僕は、気づいた時にはこの海岸にいた。 「ん……ここは……」 頭を振りながら周りを見る。そして、僕は絶望した。 僕が、絶対来たくなかった街。 僕が、何度も見た海岸の景色。 少し曇った空の下、僕は声を出そうとするが、うまく出せない。 うめきごえのような音が、ただ喉から吐き出されるだけだった。 しばらく動けずにそのまま地面とキスをしていると、誰かが走って僕に近づいてきた。 「……キセノン君?」 その声には、ひどく聞き覚えがあった。 「ひどく脱水してる……お茶、飲める?」 彼は、水色の髪を揺らしながら、僕を仰向けにする。 「ん……クリプトン……さんですか……?」 雲の隙間から光が入る。それが、目の前の少年に差し込んで、どこか神秘的な雰囲気があった。 「今は葉隠味炉と名乗っているよ。君は?」 僕の喉の奥がつっかえる感じがする。 よくわからない運命を信じてしまいそうだ。 運命なんて、あるわけないのに。 「き、喜瀬……喜瀬です」 なんとか、絞りだすような声で言う。味炉さんは、少し不安そうな顔で僕の顔を見つめ続ける。 「名前は?」 「決めて……ない……です」 僕がそう言って頭の中がぐちゃぐちゃになっていくからか気を失いそうになる。 「わわっ、しっかりして!今すぐ俺の家に連れて行くから!」 そういって、味炉さんの腕の暖かさに包まれながら、僕は気を失った。 信じていたものはすぐに裏切る。 前の代のヘリウムだってそうじゃないか。 僕のことをおいて、一人でさっさと逝ってしまって。 どうしても、繋がりを。結合の手という運命を。 僕は信じてしまう。希ガスにしては珍しいのだが。 ただ、何度裏切られても信じてしまう。 こうしてほら、こんな広い世界で、僕を抱きしめてくれるのだから。 この人が運命だと信じたい。けれど、どこかで信じられない。 悪い夢から、ゆっくり意識が浮上してくる…… ……少し薄暗い室内で、パソコンの画面だけが明るい。 カーテンを閉め切っているためだと気づいたのは、少し後だった。 「喜瀬君、大丈夫?」 僕が目を覚ましたのに気づくと、味炉さんは僕にあたたかいコーヒーを手渡してくれる。 「ありがとう、ございます」 僕は恐る恐る手を伸ばし、火傷をしないように口をつける。 「あ、テレビとか見る?って言っても、ちょっと今はあるニュースでもちきりで俺はあまり見たくないんだけど」 それでも、味炉さんに何かを追求されるのが嫌で、テレビを見たいですと言う。 薄暗い部屋の中、プラズマテレビの光が輝く。今はニュースの時間なのだろう。あまり面白くはないだろうが、それでもこの視線を味炉さんから逸らせられるならいい。 そう思って画面を見ていると、ひどく荒れた海の映像が流れる。 そこで流れていたのは、僕の乗っていた船が転覆したというニュースだった。 「え……うそ……」 行方不明者のリストがながれる。 その中に、高橋さんの名前を見つけた。 体の震えが止まらない。 そんなことって、こんなことって。 もし、僕を待たずに最終船に乗らなければ、高橋さんは。 「また、僕の我儘で、人が死んじゃった……」 何かを察したらしい味炉さんは、僕の背中をさする。 僕の瞳から、涙が溢れる。 嗚咽が肩を揺らし、罪の重さに潰れそうになる。 味炉さんが手を広げるから、思わず甘えてしまう。 彼の体はひどく暖かかった。 ずっと泣きじゃくっていた。 気づけば。外は夜になっていた。 味炉さんは、一緒に泣いてくれた。よく知らない誰かのために、祈る言葉をくれた。 僕は、それを聴きながら、泣くことしかできなかった。 ようやく落ち着いた頃、味炉さんが僕の頭を撫でながらそっと口を開いた。 「君の名前は『小石』なんてどうかな」 僕ははっと顔をあげると、味炉さんは僕を真剣な眼差しで見つめながらそう言った。 「喜瀬、小石……小石、ありがとうございます」 味炉さんからもらった名を胸に抱きしめる。 「小石君、泣き疲れただろ?一緒に外にご飯でも食べに行こうか?」 外という言葉に、僕の体が震える。 「……外は、怖いか。そう……だよね」 味炉さんは、しばらくうちにいるといいよと言って、台所で調理を始めた。 包丁がまな板をたたく音と、鍋で何かを茹でる匂い。 僕はぼうとテレビを見ている。内容の変わらないニュースがずっと流れている。 何度見ても苦しくなるだけだ。それでも、目のやり場に困って、テレビを見る。 そうしていると、味炉さんが二枚の皿を持ってやってきた。 「はい、小石君。素パスタだよ。食べれる?」 味炉さんも同じものを自分の前に置くと、手を合わせてスプーンとフォークで器用に食べていく。 かつて部下だった味炉さんは、そういえばこういう所作も毎回丁寧だったなと思い出す。 僕もフォークをもらうと、くるくると回して食べ始める。 「あ、おいしい、おいしいです。味炉さん」 「ごめんね、こんなものしかなくて。今は小石君のこと、ほっとけないから……外に出れるようになるまで、待つからね」 「は、はい……」 味炉さんは、本当にこういうところまで気が回る……そう思って、パスタを啜る。 「?小石君、どうしたんだい?」 気がつくと、味炉さんに視線が向いてしまう。味炉さんをついつい見つめてしまう。 どうしよう、胸の鼓動がおさまらない。 ぎゅっと胸を抑えると、味炉さんが優しく僕の前髪に触れる。 「お風呂入ったら、寝よっか。小石君疲れてるでしょ」 そう言って、味炉さんはお風呂を沸かしに行った。 僕は、またぼうとテレビを見ていた。 窓の外は雨は降っていないものの、薄い雲が星を覆い隠していた。 夢の中で、船での出来事を思う。 あの時の後悔は消えない。けれど、きっとこれも定めだ。 高橋さんが、無事に見つかることを祈るしかない。 そうして、僕はまた飲み込まれそうな海の深い青を思う。 これまで……この体に生まれ変わってからは初めて、清潔でやわらかいお布団で眠りにつけた。 ふかふかのお布団の心地よさに身を委ねていると、味炉さんが僕を呼ぶ。 「小石君、起きれる?朝ごはん食べない?」 ふわふわのパンの香りがする。うっすらと目を開き、味炉さんを見ると、味炉さんは優しく微笑む。 「小石君は、パンにはベリー系のジャムが好きだったよね」 そう言って、味炉さんは手際よくいちごのジャムを塗る。 僕が口の横をジャムでべとべとにしながらパンを頬張っていると、味炉さんがタオルを持ってくる。 そして、少し不安そうな顔で僕の口を拭う。 少し言うのを躊躇っていたみたいだが、意を決したのか、口を開いた。 「小石君、外は……怖いだろうけどさ、ちょっとだけ市役所に行かない?まだ、戸籍出してないでしょ?」 ここで言う戸籍というのは、元素としての今の体の登録みたいなものだ。僕は名前がなかったのもあるが、居場所を知られたくなかったので出していなかった。 「やっぱり……行かなきゃダメですかね?」 「……こればかりは、いろいろ不都合があるからね。元素専用のSNSっていうのも最近できたし……それの登録とかあるし」 僕は深くため息をつく。が、膝の上で拳をグッと握りしめると、僕は顔をあげる。 そうだ、見つからなければいいんだ、彼に。 「わかりました、行きます」 稀気市庁舎に行く覚悟を決める。希ガスの部屋にさえ行かなければいい。 準備をして外に出ると、青い空が僕を見下ろしていた。 爽やかな夏の風が通る。太陽は少しだけ痛い。 一歩ずつ、少し恐れながらも前に向かって足を進める。 時々味炉さんが「ゆっくりでいいよ」と声をかける。多分、今の僕は大分表情がこわばっているのだろう。 さらさらと水が流れる音が聞こえてくる。稀気川を越えると、すぐ稀気市庁舎だ。 二人の銅像の出迎えを抜けると、自動ドアが開く。 味炉さんがこっそり僕の耳元で囁く。 「元素専用の十八番窓口はこの奥だから、俺はここで誰か来ないか見張ってるよ」 その言葉にひどく安心してしまう。味炉さんの心遣いに感謝する。 僕は少し早足で、奥の十八番窓口を目指した。 「えっ……」 「キセノン……さん?」 確かに味炉さんは「ここに入ってくる人がいないか見張ってる」って言った、確かにそう言ったよ! でも、先に誰かいるところまでは確認してないじゃないか! 僕はひきつる声を漏らしながら、一歩ずつ後ろに下がる。 一番会いたくなかった人。 一番記憶に残っていた人。 ネオンの彼が、そこに立っていた。 「キセノンさんですよね!僕、ずっと君を探して……」 「こ、来ないでください!」 僕の声が震えながらも拒絶を示す。ネオンの彼は、少し傷ついたような顔をするも、僕に近づかないようにする。 「……ごめんなさい、キセノンさん。僕は……今は、新田天と名乗ってます、それだけ」 そう言って、天は駆け足で僕の横をすり抜けて走り去ってしまった。 天が走って行ったのに気づいたのだろう、味炉さんが焦った顔でこっちに駆けてくる。 「大丈夫かい?小石君……まさか、天君がいるなんて気づかなかった、俺のせいだね、ごめんね」 そう言って、味炉さんは僕の背中をさする。 ひどく、顔が冷たい。血の気が引いているのだろう。 あんなに天はフレンドリーに話しかけてくれたのに、僕は勢いで拒絶してしまった。 罪悪感と後悔が募る。 「でも、天くん、何でここにいたんだろうね、彼は特に用事なんてないはずだけど……」 「わか、りません……とりあえず、手続きだけして、きます……」 そう言って、僕は窓口へ向かった。 市役所をあとにした。 元素たちのための部屋……希ガスの専用十八番会議室には、行かなかった。 いや、行けなかったという方が正しいだろう。 僕のことが心配でたまらないのか、味炉さんが手を繋いでくれる。 ほんの少しだけ、安心感がある。心を満たすほどのものではないが、僕の存在が今ここにあることを示してくれる。 真上にある太陽からは、容赦なく日差しが差し込んでくる。 「小石君、何か食べたいものはある?」 そう言って、スーパー稀気にやってくる。 食べたいものがすぐには思いつかない。 「えっと、それなら、お魚……とか?」 僕がそういうと、味炉さんは「わかったよ」と言って鮮魚コーナーへ向かう。 ちょっとだけお菓子コーナーを見てこよう。そう思って足を運ぶと、青から紫のグラデーションの髪の少年を見つける。 彼に見つからないようにその場を離れようとすると、彼は勘がいいからか、こっちにすぐ気づいて近づいてきた。 「お前、キセノンだな。今……帰ってきたのか?」 「……まぁ、そんなところです」 アルゴンの彼の強目な口調は、どうしても敵対心が沸いてしまう。以前敵同士だったのもあるのだろうが。 「……飯矢、今そう名乗ってるから。お前は?」 「小石、喜瀬小石です」 飯矢の目が僕を見定めるように上から下に動く。そして、無遠慮に口を開く。 「ところでお前、天には」 「やめてください!」 飯矢の言葉をすぐに拒絶してしまう。心に残った傷は相当深い。 今すぐこの場から逃げ出したい。そう思った時には、僕の足は出口へと向かっていた。 飯矢がそんな僕の腕を掴んで耳打ちする。 「天は、お前のことを待っていたんだよ」 それだけ言って手を離す。 味炉さんが、飯矢の後ろに立っているのに気づいたが、あの場からは今すぐにでも逃げ出したかった。 なんとか走ってたどり着く温泉街。 息を切らせてそこに辿り着いた。木製の少しペンキが剥がれたベンチに腰掛け、息を整える。 はぁ、はぁと少し胸が苦しい。まだ昨日の疲れが取れてなかったか。 ……味炉さんは、追って来れなかっただろう。置いてきてしまって、申し訳ない。 そう思いながら、僕はふうと深く息を吐く。 ふと、人の気配を感じて隣を見る。 ラドンの彼が、少し間隔をあけて隣に腰掛け缶ジュースを飲んでいた。 「……キセノン君だよね?飲みますか?」 そう言って、彼は炭酸のジュースを僕の横に置く。この辺の老舗の喫茶店の制服だ。バイトの休憩中なのだろうか。 「ありがとうございます」 そう言って、カシュッとプルタブを開ける。喉にパチパチとした刺激を感じる。 「飯矢さんからさっきSNSの方でダイレクトメッセージが希ガス全員に飛んできてて、ちょっと休憩の時に探してたんですよ?」 ラドンの彼は楽しげにそう言う。 名札を見る。「谷理」と書いてある。 「谷理君、あの、できればここに来たことは誰にも知らせないでくれませんか……?」 谷理はサイドの紫の髪を揺らしながら少し驚いたように目を見開き僕を見る。 「うーん、まぁいいですけど……何か事情でもあるんですか?」 「事情……ってほどではないんですけど、ちょっと、会いたくない人がいて……」 谷理は何かを察したような、でも確証がないような顔をする。 「えっと、それは二胡さん?天君?どっちですか?」 二胡さんと言うのはきっとヘリウムだろう。 「……どっちも。っていうとあれだけど、どっちかっていうと天君に会いたくないです」 僕はため息混じりに言う。 「まぁ、あんなことがあれば、仕方ないですね。とはいえ、貴方も結構繊細ですよね」 もう十年近く前のことをいまだに引きずってる。谷理はそう言って、持っていた缶に口をつける。 「二胡さんは、今大学にいるはずなので……多分もうすぐ講義の時間も終わりますね。校門前で待ってるよう送っておきます」 「うぅ、やだなぁ……」 谷理が携帯端末をいじる。慣れた手つきで入力する。 「じゃあ、そろそろ行ってきます。谷理さん、ジュースありがとうございました」 「いえいえ、君のことを待ってる人がいるのを、ちゃんと覚えていてくださいね。小石君」 そういって、谷理もバイト先の喫茶店に向かって歩いていく。 そろそろ日も傾き始めていた。 僕は、稀気大学に向かって坂道を歩き出した。 山の木々が風に揺れてサラサラと鳴る。 何十年ぶりかに訪れた大学は、建物も定期的に新しくなっているのか、前の代で通っていたときとはかなり建物も変わってしまっていた。 正門の方にやってくると、ヘリウム……二胡さんが、本を片手に立っていた。 「えっと、二胡さん?」 声をかけると、彼は少し癖のある赤紫の髪を少し躍らせ、僕の方を見た。 「キセノン……今は小石君だったっけ?」 そう言って本をカバンに片付ける。チラリと見えた量子力学のタイトルに、なんだか難しいことをしているんだなと思う。 「さて……先に言っておかなきゃいけないこと、あったね。ごめんね、小石君。君を、置いていってしまって」 二胡の眉が八の字に垂れ下がる。申し訳なさそうな声は、少し震えていた。 「あのあと、なんとか十年経って帰ってきた時には、君とネオンが死んじゃっててさ……そのあと味炉に詰められたんだよ。なんてことしてくれたんだって」 「味炉さんが?」 僕は思わず声に出してしまった。味炉さんが、僕のことを? 「ほんと、俺が原因で不安定になったことも、ネオンの彼と……あんなことになったのも。全部、その時初めて知ったんだ」 二胡さんは門にもたれかかる。少し、表情が読めなかった。 「俺が、君を置いていかなければよかった。俺は一人で平気だったけど、君は……人の繋がりを比較的求めてしまうのに気づかなくて……だから、本当にごめん!」 そう言って、二胡さんは深く頭を下げる。 僕は、その頭にそっと手を伸ばす。柔らかい髪の中に指を沈めて頭に触れると、やっぱり震えていた。 「大丈夫ですよ。二胡さん……もう、だいぶ経つじゃないですか」 二胡さんが今にも泣き出しそうな目を腕で拭うと、僕を軽く抱きしめてくる。 「本当に、ごめんな」 「もう謝らないでください」 そう言って、二胡さんの背中に腕を伸ばす。 「そういえば、その小石って名前、味炉がつけたのか?」 二胡さんの言葉に驚いてしまった。胸がどくんと脈打つ。 「え、ええ、そうですけど……」 「やっぱり。味炉のつけそうな名前だと思った」 そう言って、二胡さんは目を細める。 意図がわからず困惑する。二胡さんは耳を貸すよう手招きする。 「味炉、ずっと言ってたよ。君のことが恋しい、恋しいって」 顔が熱くなるのを感じる。小石、恋しい。 愛おしく思われてたのが、どこか胸を満たしていく。 「ほんと、ですか?」 信じられない運命が、確信に変わる。 「ほんとだよ」 二胡さんの言葉を、信じてしまう。 「味炉だけじゃない、飯矢も、谷理も、天ももちろん俺も。みんな君を待ってたんだよ!」 そこは味炉さんだけでいい……そう思ったが、僕のことをここまで多くの人が待っていてくれたと言うのが、純粋に嬉しかった。 「……天君にも、会いに行きたいです」 僕は、絞り出すようにそういった。 二胡さんは、よく言ったと言わんばかりの顔で、携帯端末を取り出す。そして、指をパチンと鳴らしながら、いくべき道を指差す。 「天ちゃんなら、最初に君と出会った場所にいるよ」 それを聞いて、僕は息が切れるのも忘れて走り出した。 稀気市庁舎十八番会議室。 希ガスのためのそこは、僕も昔は確かによくお世話になった。 今もあまり変わらないのだろうかと思いドアを開ける。 キィとなって開かれた部屋は薄暗く、いくつかのネオン管が光を放っていた。 「……天君?」 僕はそこにいるであろう彼に声をかける。 机に座りながら、赤いネオンに横顔を照らされている天が、ゆっくりとこっちを見る。 表情は少しだけ暗い。この部屋のせいではない。僕が、拒絶したからだ。 「天君。ごめん、話に来た」 「小石君。大丈夫……何ですか?」 天君は少し緊張したような声で言う。 「うん……ほんとは、ちょっと怖いけど、大丈夫」 そして、僕も一度口で空気を吸う。どうしても、思いを口に出すのは……何度も傷つけてしまった人に思いの丈を話すのは、怖いから。 覚悟を決めて、言葉を紡ぐ。 「君を、僕の我儘に付き合わせてごめんなさい。君には幸せになってほしかったのに。巻き込んでしまってごめんなさい、そして……今も、僕を待っていてくれてありがとう」 天は、ほんの少し目を伏せ、首を振る。 「小石君のせいじゃないよ、あれは、僕も選んでのことなんです。そんな顔しないでください。僕は、また君に会える日を、ずっと待っていたんです」 天が光の中で言う。 「ずっと、君が戸籍を作りにくるのを、この街に来てから毎日、十八番窓口で待ってました」 それを聞いて、僕は顔を上げた。 天は笑顔でそこに立っていた。 「強いね、天君は。君は強いよ」 「小石君の方こそ、ずっと寂しくなかったんですか?一人ぼっちで」 「……寂しかった。本当はすごく寂しかった。ずっとぽっかり穴が空いてる気分だった。何かで埋めたい、でも、君には……申し訳なくて会えないから、ずっとここに来れなかったんだ」 僕がそう言うと、天は潤んだ目を細める。 「僕のせいでもあるんですね、小石君、僕の方こそ、ごめんね」 僕は、天君の元に駆け寄ると、その細い体を抱きしめた。 「あはは、痛いよ小石君」 天も腕を伸ばし、抱きしめ返してくる。 ざわざわと人の気配がする。 振り向くと、そこには他のチーム希ガスのメンバーたちが立っていた。 「よっしゃ!天ちゃんと小石も仲直りできたみたいだし、この部屋で酒を持ち寄って乾杯しようぜ!」 「あっ、それって二胡先輩の奢りですか?ピザ頼んでいいですか?」 「もー二人ともダメだよ、今の体はまだ未成年なんだから」 「僕の喫茶店のケーキ持って来ましたよ、これでも食べませんか?」 そう言ってざわめく仲間たちの元に、天君が右手を引いていく。 「おかえり!小石君!」 それからしばらくの後、僕は飛行機に乗っていた。 手に持っていた新聞には、大きな見出しで「奇跡の生還!」の文字とともに、高橋さんの写真が載っていた。 そんな新聞に挟まれたメモを見る。これから向かう先の住所のメモだ。 そこで、新しい僕らの仲間が目覚めるらしいと聞いた。 遥か遠くの街を目指して、雲の上を行く。 今回は、僕が適任ということで、向かうことになった。 元素としての目覚めのある種一つの段階。 名前がつく、そこに立ち会うことになった。 二胡さんなんかは、いいなー行きたいなーって最後まで駄々を捏ねていたけど、残念ながらチケットは一枚限りだったし。 たどり着いた先、僕が施設の人に案内され通された部屋の中では、まだ少し輪郭の曖昧な少年が立っていた。 「君が、僕たちの仲間なんだね」 そう言って、僕はその輪郭に触れる。 「これからは、僕らが君の困った時には助けに来るよ」 少年の鈍く光る黒色の瞳に光が入る。 「オガネソン。それが僕の名前」 少年は一瞬光ったかと思うと、曖昧だった輪郭がはっきりした。 「オガネソン。いい名前です」 僕は彼の右手をとる。 「共に歩みましょう、僕たちと、この世界を」 僕は、彼を外の広い世界へ連れ出した。